幼稚園に通わせていて悩むのが、子どもが…
「幼稚に行きたくない!」
と言った時…そんな場面がないならもちろん良いですが、やだ!となる事もありますよね。
今回は、新年度、イヤだ!が出がちな小さい組の様子から、なんでイヤだが起きるのか、なかの幼稚園ではどうやって大丈夫になっていくか、ということについて書いてみます。
もっと違う場面のいやだ!は、また別の理由の時もありますが、今回は新しい生活に対してのイヤだ!です
新入園&進級で「イヤだ!」が出る時

今回、写真の子は直接文とは関係ありません
幼稚園に来る年齢の子どもたちは、基本的にはやりたい事ができて、安全な場所には、喜んできてくれます。けれど、4月の新年度、ぎやー!と泣いて嫌がる子もいます。
何人かの様子から、その理由を考えてみます。
思ってたのと違う!からの拒否感

今まで、いつもお母さんと一緒にいた、という子は、幼稚園に行くというのも、いつも通りお母さんも一緒に行くと思っているのがほとんどです。
それが、お母さんはいない中で自分だけで過ごすという事の不安が出るでしょう。
また、満三歳や保育園に通っていた子は、今までと違う、という事に戸惑うでしょう。どちらも、3歳の年齢の子には自然なことです。
3歳なりに「こうだろう!」と思っていたことと違ったその時に、その戸惑いや不安感を、まだうまく言葉で整理したり伝えたりできない3歳には、「泣く」または「拒否する」という事で表現します。
心配や泣きたい気持ちは受け止めつつ、楽しいことや安心なことを伝えていくと、自然と泣かずにいられるようになります。
楽しいことが積みあがれば、行きたい!となっていきます。
今年の新入園の子と進級の子の様子を紹介

新入園の「Aちゃん」の様子
初めての日は、よくわからないまま過ごし、ニコニコと遊んでいたAちゃん。テラスの前にあった、お砂のごちそう作りや、粘土遊びで遊びました。
2~3日して。お母さんと離れたくない!と、気が付いたAちゃんは朝門をくぐるときに大泣きに。先生が抱っこで受け取り、しばらく泣いていました。
しばらく・・。30分くらい泣いていたかな。抱っこされながら、園庭にあった、コロコロと丸い球を転がすおもちゃが目にとまり、ちょっと涙が止まりました。

コロコロしてあそぶ
それを見て、先生が似たようなおもちゃを部屋の前のテラスに作ってみました。コロコロ。Aちゃんは、コロコロしては球を拾い、しばらく遊び、ふと思い出して『ママ~』と泣いて・・を何回か繰り返していました。
次の日。朝、門のところでお母さんと離れるときに泣いていたので、先生が受け取っていました。泣きつつ、コロコロのおもちゃをみて、遊び出していくAちゃん。
その次の日。門では泣きつつ、先生を見ると手は先生の方に差し伸べて、「だっこして」を表現するAちゃん。
この日は、結局、朝別れ際に涙がありましたが、遊んでいる間は涙が出ずにいました。

進級の「Bくん」の様子

B君は、なかの幼稚園で過ごしてきて、進級して年少組になりました。
4月、登園して、新しい部屋に行ってみよう!と、前のクラスからみんなでお引越ししました。新しい部屋、新しい先生。新しい先生も、よろしくね!とたくさん遊んでくれそうです。
が、B君は…
お家に帰って、泣きました。ヤダヤダ!
夜も眠れず。ヤダ!明日行きたくない!!
これは、B君にとって新しい部屋や新しい先生が、思ってもいなかったから。
前年度、なかの幼稚園では進級するよ、とは小さい組にはあまり言いません。
もちろん、兄妹や年長組が話していて「こんど、○組になるんだ!」という話題は身近にあります。新しいバッチや進級用品をもらって何となく嬉しかったりもします。
でも、ことばでそう言っていても、まだよく理解しきれないのがこの時期です。いざ、新しい部屋に引っ越してみて、戸惑ったんですね。

新しい部屋でお集まり

というB君の戸惑い、お母さんもびっくりしてました。
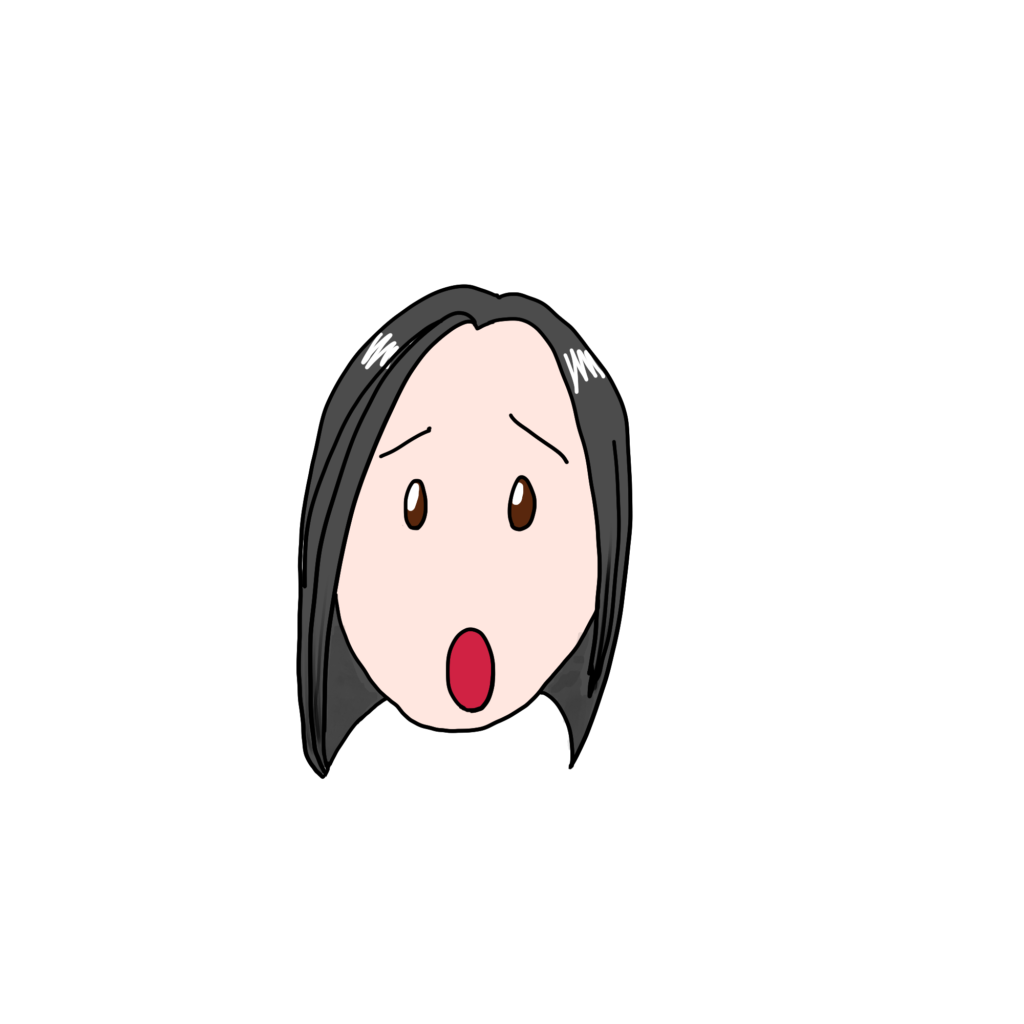
と、本当に心配そうに送ってきた、新年度二日目。やっぱりB君は新しい部屋について、大きく泣きました。
でも、そこでお母さんは離れて、B君はいつも通り幼稚園で過ごしました。
そうしたら、B君なりに幼稚園はいつも通り、部屋は変わったけど、いつも遊んでいたトラックもブランコもある、と思えたんでしょう。
みるみる、お家で泣くことが減っていったそうです。4日目には、自分で門からお部屋へすたすたと登園していました。


びっくりしたんですよね、B君。でも、B君はあっという間に「大丈夫」を取り戻していきました。
これは、お母さんが泣いたB君の不安をしっかり受け止めつつ、いつも通りの生活を送ってくれたから。
好きな遊び、やりたいことがいつも通りできる、と分かったら、あとは安心できる。ここで、3つポイントがあります。

1:びっくりさせるなら、予告しておけば?
これは、年齢によります。もう少し大きくなったら、有効でしょう。
年長組に進級するときは、みんなが「次は年長、そら組だ!」と期待を持って進級します。けれど、小さい頃は、まだ今日明日の感覚が育っていません。
そこに、4月から新しいお部屋だよ、と言っても、何かが変わるらしいという漠然とした理解になり、それは不安につながることが多いです。
楽しいことの予告は、日にちを間違えてもそんなに心配にならないので、してもいいでしょう。
生活が変わる、というような大きな変化は、わからなくて不安になるなら、予告しないで体験してみてわかる、というので良いと思います。

2:お母さんが不安を感じつつも送り出してくれた。
第一子のB君の不安にお母さんも不安を感じたでしょう。二日目の朝、お母さんも泣きそうな不安顔でした。でも、幼稚園に行けばきっと大丈夫、と送り出してくれました。
きっと、ここでB君の不安に巻き込まれて、「休もうか?」とか「お母さんもいるよ」といった事が続いていたら、B君は新たな混乱が起こっていたでしょう。
不安があっても、いつも通りの生活をしてくれたおかげで、B君にはわかりやすかったと思います。
大人の不安は、子どもにも伝わります。大人が不安な気持ちで子どもと向き合うと、子どもも不安になります。
お母さんが不安を抱えている場合、離れ際にすごく泣く子がいますが、これはお母さんが「ここで離れていいのかしら、わたしこれでいいのかしら」と心配なのを子どもが引き受けて泣いている、という事が多いです。
不安はあっても、幼稚園を信頼してどんと預けてください!
3:遊びたい遊びがある
Aちゃんでも書きましたが、遊びたい遊びや楽しいことがあると、不安や心配を払しょくしてくれます。
B君は、前の年にちゃんとたくさん遊んで、自分の遊びがあったんですね。トラックを持ち出して、友達を誘って走り出す姿は、かっこよかったですよ。
知識があるより、何より、自分の遊びがある事。これが、ちいさいうちの一番の強みです。
時々、いつもは元気なのに、朝ひどく泣いたりぐずったりする時。
こういう時、しばらくして熱が出たり嘔吐したりすることがあります。体の不調があって、いつもと違うというのが泣きやぐずりにつながっていた、という事ですね。
あれ?いつもと様子が違う、という時は、そんなことも気にかけるといいですね。あまりに、朝の体調不良が続くときは、違う理由があるのでそれも考えてみましょう。
園長先生のつぶやき

ここで、この年齢の子の生活で大事な要素があります。
「一定して送り出す」が重要です!
いつも同じ生活の中で「幼稚園に来る」というのが一定であれば、子どもは自分なりに生活を掴んでいきます。
これが大人の都合で「今日は来るけど明日は来ない」「今日は朝早いけど、明日は遅くに来る」と一定にならないと、子どもには毎回状況が違う中で戸惑いが続き、なかなか安心を実感できない、という事態になります。
特に、まだ概念で物を理解できない2&3歳児には、言葉で「明日はね」なんて説得しても実感できません。経験して知っていく時期です。

ここで心配なのが、「2歳3歳でいつでも預けていい」という風潮が広がりそうなこと…
「子ども誰でも登園制度」というのが始まります。2026年度から本格的に始まる予定の行政の子育て支援制度なんですが、
「2歳&3歳の安心を実感するまでにじっくり時間がかかる=安心な世界を積み上げていく年齢の子達」
この子達を、いつでもというか、大人の都合で人に預けても大丈夫、という風に保障しているようで心配です。
2歳3歳で集団生活に入ることはできますが、その時には、その年齢の子にふさわしい配慮がいるんです。
大人が「今日は3時間ここで過ごすんだね」と時間や状況がわかっている中で普段と違う場所にいるのと、まったく違うんです。
時間の概念がまだ実感できない子たちを、不安な中で親から引き離して育つのは、親と離される不安感や不信感です。
それは、次に親を見たら離れないぞ!としがみつかせることになります。預けることでかえって、親の普段の負担を増やすことになります。

また、子ども側にも、泣いても訴えても不安であるというのを何回も経験させるのは、自分が大事にされないという事になるので、良くないと思います。
親の負担を軽減したい、というのは、ありがたいことですが、方法がちょっと違っているのでは…
「毎日、親子共に楽しいと思える時間が増えることが本当の負担の軽減だと思います。」
その時に、必ずしも親と子どもが離れてなくてはならない、というわけではない。
子どもや親をサポートする行政の側に、ホントに子どもの事を分かっているアドバイスがあるのか、最近の子ども子育て支援制度の迷走ぶりが心配になります…



















お母さんがいて安心という世界から、すぐそばにお母さんがいないという幼稚園へ。
その不安は大きいでしょう。小さい時は、その状況を理解するのに数日かかることもあります。あれ?お母さんがいない!と気づいたり、思っていたのと違う!と気づくのに、数日。
それから、お母さんがいなくても安心していられるし楽しいことがある、と実感できるのに、また数日。
その間は、泣いたり嫌がったりもありますが、一定して送り出してもらえれば、安定していけるものです。そして、「遊んで楽しい!」という実感がちゃんとできたことは大事なことです。
お母さんと離れることがわかったとしても、過ごしている時間が苦痛では、行きたいとはなりません。
だから、コロコロなど遊んで楽しい、「その子の楽しい!」を用意します。
Aちゃんは、幼稚園の入園前に、プレ「親子の広場」によく来てくれていました。
そのときに、お母さんと一緒にたくさん遊び、ここは楽しい所だ、というのはすでに作れていたんでしょう。
入園前に、ここは安心して過ごせるところだ、と思ってもらえると一度不安になっても、また取り戻せます。「遊んで楽しい」というのは、とっても大事なんです。